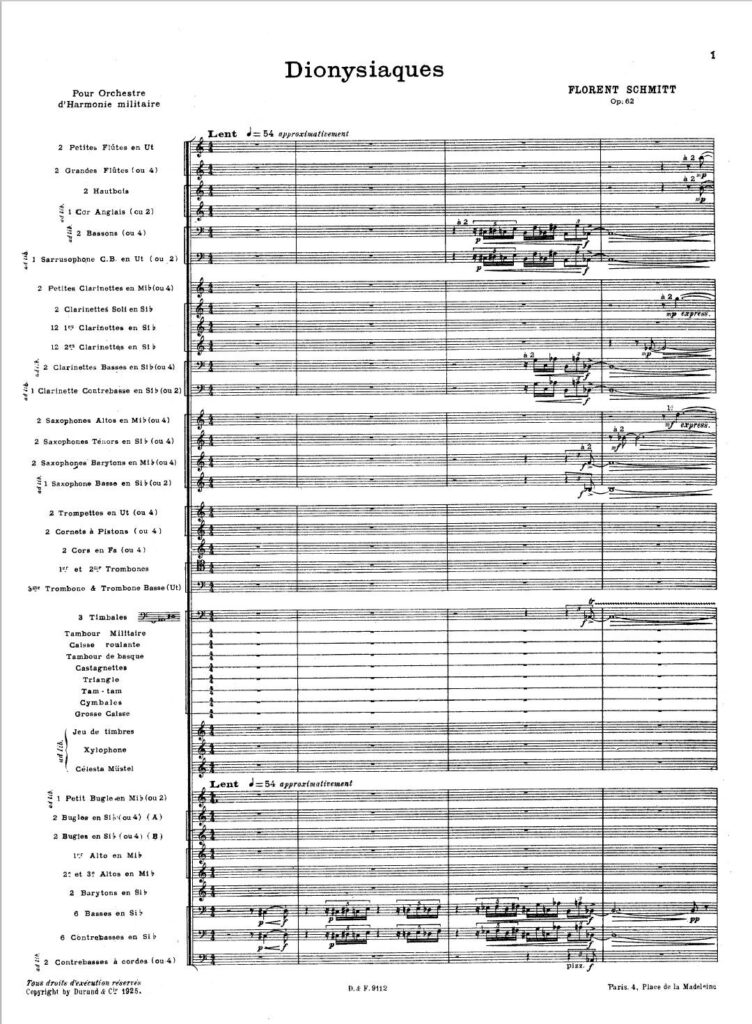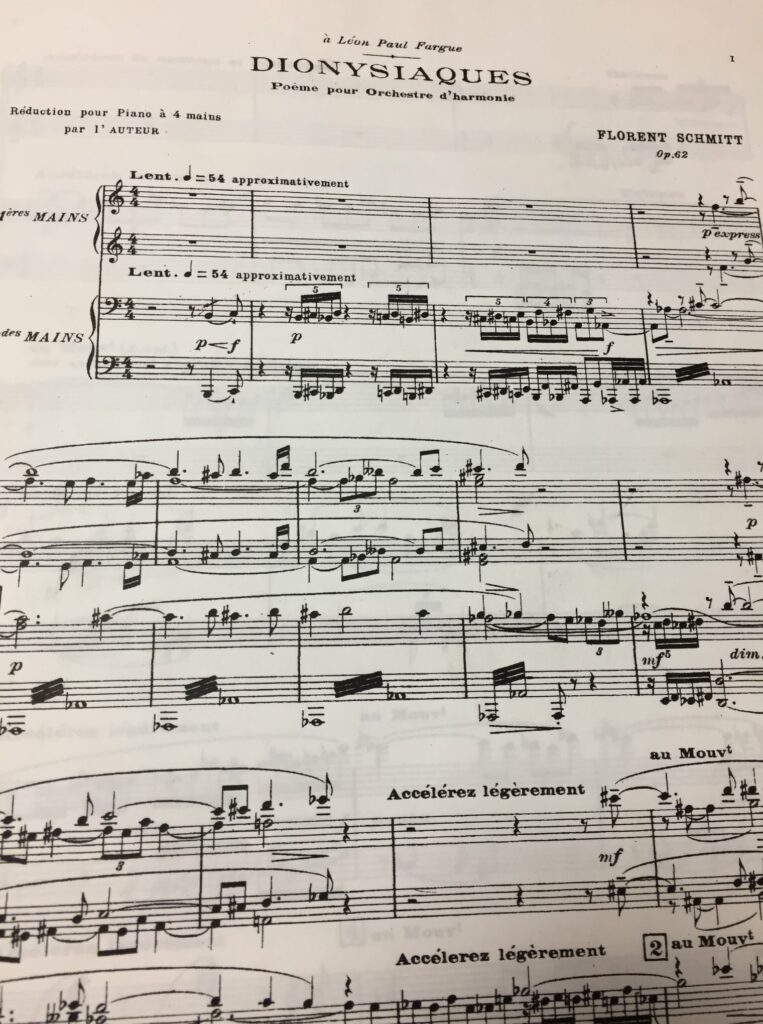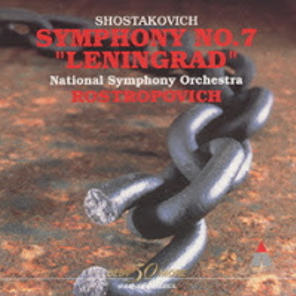(2021年3月23日)
先日は、楽譜の誤植の件に触れたが、Facebookの別の友達のところでは、作品タイトルの「誤訳」についていろいろと話がひろがっていた。
「誤訳」というほどでもないかもしれないが、私には忘れられない曲がある。
ドン・ギリス(Don Gillis 1912〜1978)作曲の『The Man who invented Music』というナレーション付きの曲だ。
日本では『音楽の創造者』や『音楽の発明者』といった訳が一般的かな…?
しかし、話の内容からすると、どうもしっくりこないのですよ(笑)
孫娘のウェンディを寝かしつけてゲームを楽しもうとしていたおじいさん。そのウェンディに「(枕元で)お話をして」とせがまれる。お話ではなく子守唄を歌ってあげようとするがウェンディは、「子守唄なんて知らないでしょ?お話をして」と…。「私が子守唄を知らないだって?私は子守唄を発明したんじゃぞ!いやいや、音楽を発明したのはこのわしなんじゃ!」とおじいさん。「じゃあ、どんなふうに音楽を発明したのかお話しして」とせがまれ、400万年前に遡って話を始めるのだ。
オーケストラで使われる楽器や行進曲、ダンス音楽、コンサート、果ては有名な作曲家までが全てこのおじいさんの発明らしい…(笑)
このようなストーリーからすると、「創造者」や「発明者」という訳は少々堅苦しいではないか(笑)。
私はストレートに、『音楽を発明した男』とした。
一気にコミカルな感じが出たような気がする。
「直訳」がしっくりくるケースもきっとあるはずなのだ!
ギリスというと、吹奏楽に携わっている方であれば、『台所用品による変奏曲』が最も知られているかもしれないし、『ジャニュアリー・フェブラリー・マーチ』(以前の吹奏楽コンクール課題曲『マーチ・エイプリル・メイ』のタイトルは、きっとこの曲がなければ生まれなかったと思う)、管弦楽からの編曲ではあるが『交響曲第5 1/2番』、『タルサ 〜石油についての交響的肖像』などをご存知の方もいらっしゃるだろう。また、「カナディアン・ブラス」のアレンジャーであったことを知る人もいるかしら…?
少々ご年配の音楽ファンの方であれば、かのトスカニーニの右腕として「NBC交響楽団」のプロデューサーを務めたり、第2次大戦後初めて来日した海外のオーケストラである「シンフォニー・オブ・ジ・エア」の会長として来日したことをご存知の方もいるだろう(来日時、指揮台にも登って自作を指揮しているようだ)。
ギリスの作品については、近年アメリカのAlbanyから随分とCDが発売されている。
 | 新品価格 |
 | 中古価格 |
純粋なクラシック音楽というよりは、「ライト・クラシック」といった範疇の音楽かもしれないが、古き良きアメリカを偲ばせる作品が多い。同時代のモートン・グールド(Morton Gould 1913〜1996)の作品と併せて聴いてみると、アメリカの「大きさ」が感じられるような気がして面白い。
 | グールド:アメリカン・バラーズ/フォスター・ギャラリー/アメリカの挨拶 新品価格 |
さて、『音楽を発明した男』であるが…。
私はこの作品を、大分県警音楽隊在職時の定期演奏会で取り上げた。それこそ、写譜があまりにも酷い團伊玖磨氏の行進曲『べっぷ』を演奏した時と同じ演奏会だ。
この曲を取り上げようと思った理由は二つ。
一つ目は、「楽器紹介」的な要素を持った作品であること。
演奏会のアンケートでよく「楽器紹介をしてほしい」と書かれていたこともあり、ひとつずつコメントしながら各楽器に何か一曲やってもらうよりは、一曲の中でやりたかった。
(ただし、原曲が管弦楽なので、サクソフォーンやユーフォニアムの紹介が曲中ではできなかったが…)
二つ目は、県警の警察官に「役者」がいた、ということ。
音楽隊員ではない。ちょうどプログラムの検討に入った頃、地元の新聞でこの警察官が紹介されていた。彼のことはこの記事で初めて知ったのだが、元「歌舞伎」役者だ。片岡愛之助さんのもとで修行したとのこと。記事は、彼が警察官拝命後その経歴を活かし、地域の講話などで他の警察署員らと寸劇を通して「振り込め詐欺」などの被害防止を呼びかけているというものだった。寸劇を取り入れた講話は、どこの警察でもよく行われているだろうし、大分県警には各警察署に「○○劇団」というものがある(あった)。音楽隊の演奏会に出演していただくこともよくあった。
「彼に手伝ってもらいたい」と思い、上司に相談し彼が所属する警察署に交渉。ありがたいことに即決だった。
ナレーションの台本は私が和訳して準備したが、なかなか難しい…(笑)しかし、楽しくもある(本音を言えば、「大分弁」を存分に取り入れたかったのだが…笑)。
三交代勤務で大変な中、そして、ナレーションだけということで少し勝手が違う中、彼はしっかりと準備をしてくれた。彼は、当直明けや休みの日に音楽隊まで足を運んで練習に参加してくれた。練習後には「しっかり稽古します!」と(「稽古」というのがいいね! ちなみに、私は今だに「訓練」という言葉が出てしまうことがある)。
『音楽を発明した男』の本番、彼のおかげで(演奏のキズは多かったが…笑)お客様に喜んでいただけた(と私自身は思っている)。
随分遠回りをしたようだが、ここからが本題。
『音楽を発明した男』、実は準備段階で、演奏する側に曲に対する「拒否反応」があるのを感じていた。皆、口には出さないが、そんな空気は漂っていた(笑)。
まぁ、私の想いが強すぎたのかもしれないが…。
(楽譜を自分で買ったくらいだからそんな雰囲気になっても仕方ないか…笑)
奏者の中には、自分が「知らない曲」を取り上げることに「拒否反応」を示す者が必ずいるのは事実だ。しかし、「今知っている曲だってもともとは知らない曲だったのでしょう?」と問うてみたい(笑)。
その人にとっては、曲を知る「きっかけ」がどのようなものだったかが重要であるようだ(大抵、吹奏楽コンクールで流行ったから、昔やったことがあるから、というのがオチだ…笑)。
「楽長が持ってきた曲」というのがどうも引っかかる、というのもあるだろう(笑)。
まぁ、その気持ち、分からないでもない。
私が、演奏する側として、あるいは選曲する者として心がけているのは、過度に「ノスタルジック」にならない、ということだ。そして、「好き嫌い」を言っていては仕事にならない、ということ。
ただでさえ、警察音楽隊の演奏会には「吹奏楽」とは、「クラシック音楽」とは日頃関わりの少ないお客様が多く足を運ばれる。皆様は「警察音楽隊」というジャンルを楽しみにしておられる(と私は強く思っていた)。
そのお客様も多くは「知っている曲」を望まれる。しかし、演奏者側が強い想いを持って選曲し、演奏すれば多くのお客様が心に留めてくれるということも随分体験した。
だから、吹奏楽界隈で流行った曲を何が何でも締め出す、ということもしなかった(演奏してみて考えが変わることもあるので)。
誰も知らない曲を取り上げることが目的でもないのだ。どのような想いでその曲を取り上げるか…。そこが大切なのは言うまでもない。
『べっぷ』だって『音楽を発明した男』だって、私は演奏したことはなかった。それでも、その時は「これらを演奏することは意味あることだ」との想いが強かったのだけは確か。
「流行っているから」、「昔やったことがある」と曲(実はこれだってお客様のほとんどが知らないであろう)を持って来る者に、その意図を訪ねてみると、大抵嫌な顔をされるし(笑)。
そこに確固たる理由はない。「やりたいから」が理由だ…。
ただ、それはそれで否定はできないところもある。大きなホールで演奏できる機会は年1回、ふだん演奏できない曲に取り組める貴重な機会でもあるので。
それにしても、『音楽を発明した男』の練習の際、彼のナレーションに接した時の空気の変わりようと言ったら…(笑)。
「知らない曲」だったからこそ味わえた「変化」だったと今でも思っている。
何やらとりとめのない文章になってしまったが、「知らない曲」を取り上げることの意義、難しさ、いろいろと考えさせられたなぁ、と少々「ノスタルジック」に気分になる…(苦笑)。
 | Paul Bunyan Overture / Symphonies 5 & 6 新品価格 |
(Facebookへの投稿を一部加筆・修正の上転載しました。)