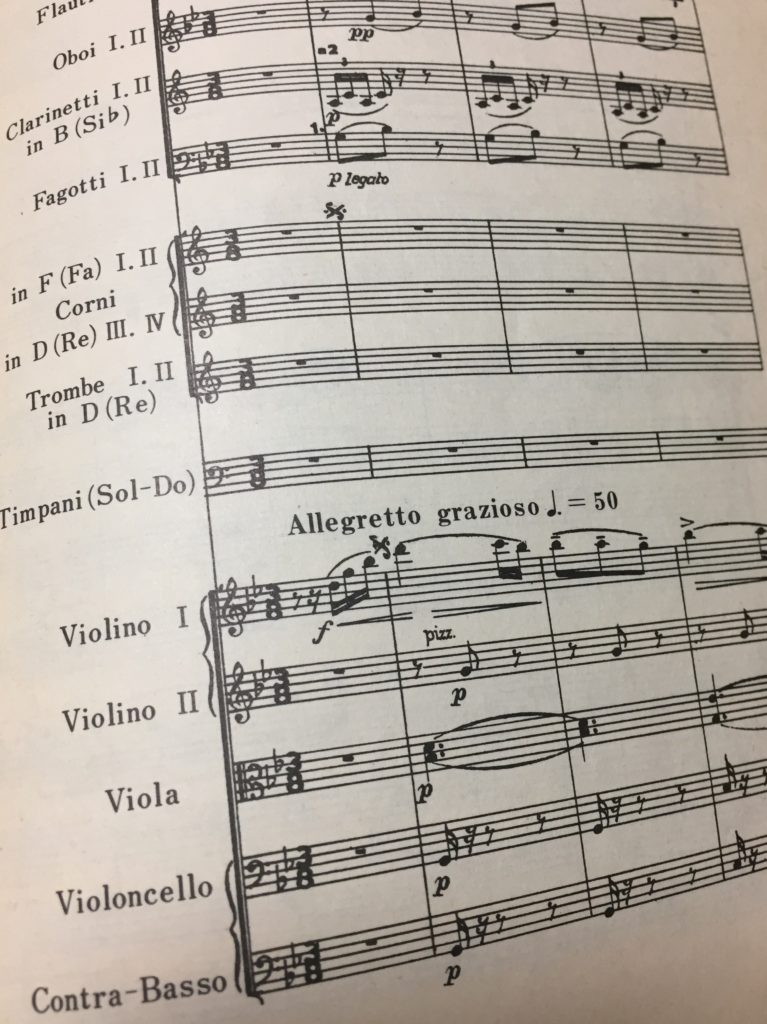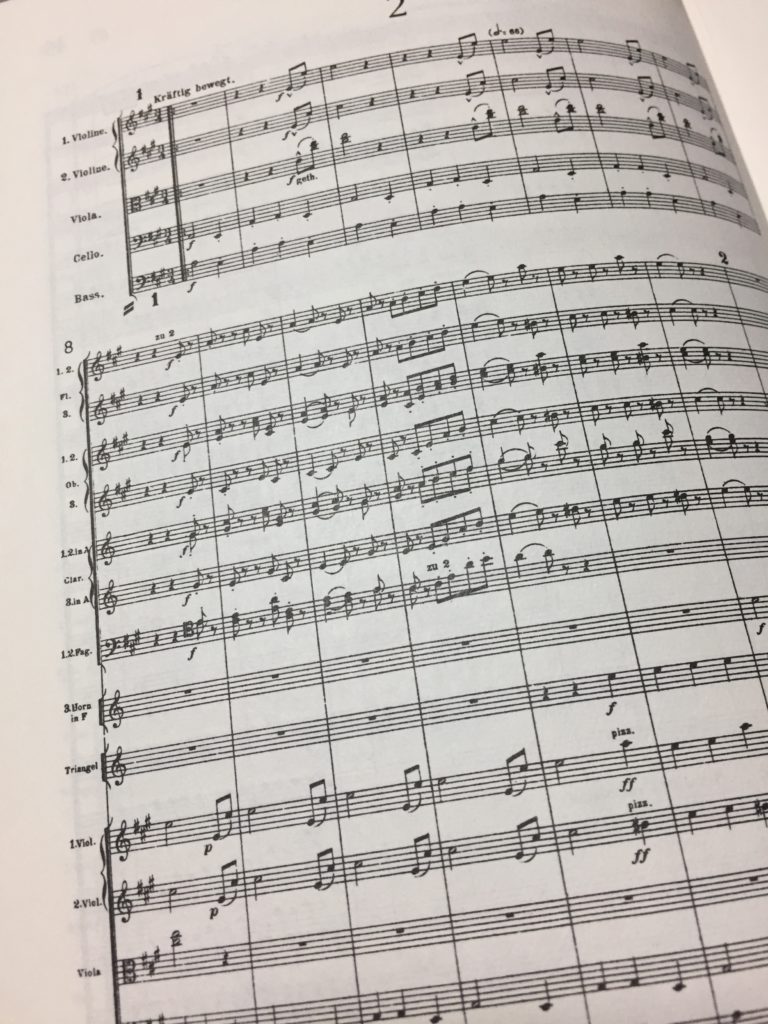
「第5回」で、「「アクセントの正確な周期的回帰」により旋律が韻律なり拍節を獲得する」というキルンベルガーの話を取り上げたが、「アクセント」云々はともかく、「拍節」が、「周期」的あるいは「回帰」の構造を持っていることは、疑いようもない。
では何が「周期性」、「回帰性」をもたらすのか…?
小節の頭にアクセント(ヒンデミットの言う「音量的」な)をつけることが周期性や回帰性を示すとは言い切れない思うのだ。
(最終的には「何らかの」アクセントが付くが、それを第一に考えるということではない、ということ。)
私は、最初に戻るための「準備」こそが周期性、回帰性をもたらすのでは、と考える。
その「準備」はどこで?
それは、「三拍子」であれば「三拍目」、ということになる。
(「歴史は繰り返す」とよく言われるが、歴史だって突然変わったわけではなく、そこに至る経過、つまり「準備」と言える時間(あるいは背景)があったはずだ!)
2年前、高校生たちと一緒に音楽を作る機会をいただいていたが、その際何度となく言ったのが、「小節の中で完結させないように!」
小節の最初、つまり1拍目を合わせること、ズレないことに意識が向きすぎて音楽が「流れない」「繋がらない」…。
これは、ここまで述べた「拍節アクセント」に直接結びつくものとは言えないかもしれないのだが、「次へ向かう」という意識が音からは感じられないのだ。
演奏者は、音楽が続いていくという意識は当然ある(目の前に楽譜もあるし…)。
ここには、音楽的な「まとまり」、フレージング、和声進行などをどう捉えるか、という問題も絡んではくるのだが、何れにしても「次へ向かう」ための「準備」が疎かになっていると言わざるを得ない。
コンサートで、アンコールを求める拍手がいつの間にか手拍子に変わっていく、という経験はよくあるが、あれがしばらく続くと、「二拍子」か「四拍子」に感じられる、という経験はないだろうか?
これこそ、既に述べた人間本来の持つ「グルーピング」の心理の顕著な例と言えるかもしれない。
そこでは、意識的に「特別な(音量的な)」アクセントを(小節の頭に)つける人はまずいないだろう。
もちろん、人によって「ズレ」はあると思うが、この手拍子を「三拍子」で打とうとする人が果たしているだろうか…
「三拍」で回帰させようとすると、むしろ三拍目の方に意識が向かないだろうか…
この意識は「二拍」の時や「四拍」で回帰させるよりも強いものだと思う。
いや、「二拍」や「四拍」の時より強く意識する必要がある、ということだ。
ここが「三拍子」の難しさなのではないかしら。
「第11回」につづく
「第9回」にもどる